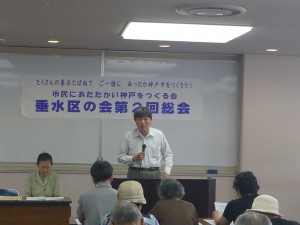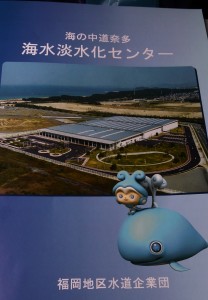福祉・くらし第一、住みよい垂水区へ
ブログ
今日は、垂水区選出議員会議が市役所でおこなわれ、垂水区における施策について、区役所からの報告をうけました。
垂水区は母子家庭等の世帯数が市内で最も多く、1574世帯にのぼるそうです。
経済的にも子育てにも苦労されている家庭が多いと思われます。
新規施策の一つとして「大学との連携による母子家庭児童等への学習意欲支援」を実施するとしています。
内容は、こどもたち同士がピアカウンセリングを通じて自尊感情を高め合い、学習意欲向上につなげていくことをねらったもののようです。
看護大学の学生がピアカウンセラーとして支援に入ります。
どれだけのこどもたちを受け入れることができるのか、こどもたちの成長と発達にとって実際にどういった効能を発揮するのか、見守りたいと思います。
 5月30日、垂水駅前や区内のスーパーマーケット、団地の前で街頭演説をしました。
5月30日、垂水駅前や区内のスーパーマーケット、団地の前で街頭演説をしました。
この日、中心的に訴えたのは、集団的自衛権行使の批判。
「自衛」とは無縁な戦争する国づくり。
憲法の解釈を勝手に変えて自衛隊の戦闘地域への派兵、武力攻撃を合理化する安倍内閣の暴走ぶりを批判し、立憲主義と平和をまもることをよびかけました。
6月1日、「市民にあたたかい神戸をつくる垂水区の会」の総会で、神戸市政報告。
市政全般の特徴・問題点、運動の到達点を40分ほどで語るのは、ちょっと厳しかったかな(**;)
「もりだくさんで、しんどかった」
あとの、「反省会」でもご指摘を受けました。
帰宅後、ウチの妻からも「あんたの話し方、なんかエラそうやわ!」と怒られてしまいました!!\(゜゜)/
結構時間をかけ、準備して臨んだので少し、へこみました。
しかし、久しぶりに市政報告をさせてもらってとてもいい機会だったと思います。
会派の視察一日め。
23日は岐阜市役所へ。
同市は自動車を中心とした交通から公共交通や徒歩、自転車の役割を重視し、歩いて出かけられる町をめざす、総合交通政策をつくっています。
コミュニティバスを地域の方々が運営し、市内で安定的に営まれており、全国からも注目されています(写真はJR岐阜駅前周辺を運行するコミュニティバスです。左・金沢はるみ、中・大かわら鈴子議員と)。
コミュニティバスは、需要は高くても、採算面や実際の運営ノウハウなど先行きのことを考えると、地域住民にとってなかなか手掛けにくいのが、実際のところです。
同市では交通政策課の職員が地域に足を運び、地域が踏み切れるところまで時間をかけて支援に入っています。
そこが神戸市にも求められているところだと思いました。
コミュニティバスを走らせるのに有利なのは市街地。
高齢化が特に深刻な地域、交通不便地となると、どうも事情が違うようです。
共産党岐阜市議員団の方のお話によると、不利な地域への手当てこそ行政に求められているところだと言われていました。
2日目は富山市役所へ。
JR富山駅は来年の新幹線開通を控え、それに照準を合わせた工事を急ピッチで進めていました。
同市は自動車依存度が高い町でしたが、高齢化が急速に進み、運転をやめる人も増えてきています。
市街中心部の人口が減ってきているようで、町の活気付かせ、利便性を向上させるためには、公共交通機関で移動しやすい街にしていく必要があり、LRT(Light Rail Transit)と呼ばれる新型の路面電車を走らせています。
バス並みの運賃で市内を円滑に移動できる交通手段として市民の間で好評のようです。
人口減少、急速な高齢化。
導入すべき同市の事情があったのでしょう。
予算市会では、商店街・小売市場や中小業者への支援策について質疑しました。
質疑内容については後日に投稿します。
ところでこどものころのことですが、「ジェームス山ショッピングセンター」という小売市場をよく利用しました。
「いらっしゃい!」「毎度あり!いつもありがとう!」
─いつも元気な声で買い物客の流れに声掛ける漬物屋のおばさんと、となりの豆腐屋さん。
学校帰りになんとなく立ち寄った文房具屋さん。
ウチでしょっちゅう出前を注文した「南球園」という小さな中華料理店。
奥の突き当たりで営んでいた駄菓子屋のおばあさん…。
私が学生の頃には順番に店舗が閉鎖していき、就職をした頃になると、まるでトンネルのようにひっそりした”倉庫”と化し、涙を流し続けているかのようでした。
量販店の進出で大打撃を受けたのでしょう。
どのようにして営業を守ればいいのか、成すすべもなかったのだと思います。
現在は、まったく面影もなく新築の住宅街に様変わりしていますが…。
神戸市はこれから商店街や小売市場の振興策に力を入れるとしていますが、個々の小売店も含めた抜本的な支援策が必要です。
6日から7日まで阪神水道企業団議会からの視察に参加してきました。
目的地は福岡地区水道企業団(福岡市を含む6市7町1企業団、1事務組合から構成される)。
人口の集中と都市化の進展、近くに大きな河川がなく、筑後川からの取水に依存していること、警固断層帯など5つの活断層が流れ、大地震の最新の備え、渇水に遭いやすい気候条件化にあるそうです。
筑後川、多々良川水系、海水淡水化施設から水を供給し、給水人口は247万9000人。
1日最大302800㎥の水道用水を供給。
ダムが多いのには、驚きました。
江川ダム、寺内ダム、合所ダム、大山ダム、下筌(しもうけ)ダム、松原ダム、鳴淵ダムがあり、さらに五ヶ山ダム、小石原川ダムを建設中であるとか…。
水道料金が高くなる要因となっているのではないでしょうか(基本料金単価157円・㎥、阪水は65円・㎥)。
実際は「基本水量調整率」を掛け合わせて引き下げているようですが(平成25年4月1日に75%→67.5%に改定)。
海水淡水化センター(まみずピア)は、平成22年度を目標年度とする福岡地域広域的水道整備計画で、海水淡水化事業が位置づけられました。
玄界灘の海水を取水して、淡水化。
総事業費408億円。
年間ランニングコスト17億円(うち動力費8億円)もかかっています。
コスト削減に相当力を入れざるをえないようでした。
一日最大50000㎥の生産水をつくる。
この日は20000㎥生産していました。
当初見通しを下回る生産量です。
適正な水受給計画になっているのか、疑問を持ちました。
海水から分離された塩分の製塩化も行われていたようだが、採算が取れなくなり、昨年事業者が撤退したとのこと。それも残念です。
今日は午後2時から全体議員総会が本会議場であり、久元新市長が施政方針を発表しました。
その中で、乳幼児医療費について、「中学校3年生までの入院医療に加え、通院の無料化を段階的かつ速やかに実施する」とありました。
現在、通院無料は2歳児まで。
しかし、現在の財政状況でも予算編成を適切に組み替えれば、「段階的」ではなく、速やかに実施することは可能です。
しかし、中3までの医療費無料化に言及したことは、これまでの長年にわたる運動の反映でもあります。
おとなりの明石市でも実現しています。
神戸市において中3までの医療費無料化が現実の日程に上るよう、これからが運動のがんばりどきです。